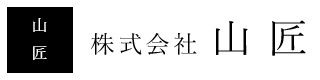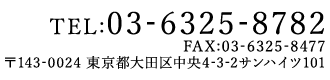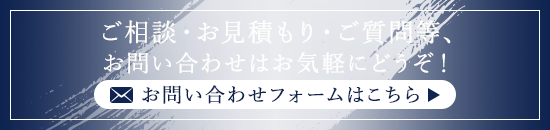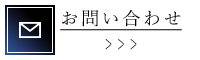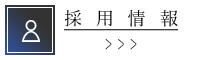前回のブログでは、植栽の整備をお伝えしました。
今回は、いよいよ土中環境の整備を実施していきます。
本施工例では、土中環境の整備を3つのSTEPに分けて実施します。
今回は長年の使用で目詰まりをし、機能不全となっていた雨どいの排水を、土中に浸透するように再整備しました。
| 物件基本データ | |
| 住居形態 | 戸建て |
| 住まいのエリア | 千葉県南部 |
| 構造 | 木造軸組(在来工法) |
| 築年数 | 40年 |
| リフォーム範囲 (坪数等) | 敷地60坪(建物25坪・2階建て) |
| リフォーム内容 | 土中環境整備による、水や空気の流れの改善 |
| ◆土中環境整備の施工のステップ◆ | |
| STEP1 | 不要物撤去 |
| STEP2 | 植栽・樹木整備 |
| STEP3 | 土中環境整備①(雨どいの排水の再整備(集水桝の作成と氣水脈の施工))←今回ご紹介 |
| STEP4 | 土中環境整備②(建物に沿った水脈の施工) |
| STEP5 | 土中環境整備③(集水桝からの排水用の水脈の施工) |
水脈の作成
|
|
土中環境整備は、地中の水と空気が縦にも横にも健全に流れるような「抜き」を作る作業が基本になります(氣水脈)。その際、直線的な溝ではなく、自然のままの河川のように蛇行した曲線にした方が、より健全で良い塩梅の水と空気の流れを作ることができます。 |
|
|
次に、水脈の所々に、竪穴を作ります。 |
 |
掘った水脈には、炭と、細い伐採木や枝葉、さらには岩石を適度な大きさに割った、「グリ石」と呼ばれる小石を詰めていきます。 コンクリート(U字溝)ではなく、自然素材を利用することで水と空気が動きやすくなり、根や菌糸が育ちやすい環境を作ることができます。 また、この時のポイントになるの が、現地で剪定や伐採した枝葉を使うことです。土中環境の改善には、土の中の菌の動きが重要になってきます。その土地の菌やミネラルで育った植物を素材として使うことで、その土地にすぐに馴染み、場が早く安定するのです。 (その土地にあったものは菌の相性が良い) |
 |
竪穴についても、炭や枝葉、グリ石や瓦を同様に敷き詰めます。 |
集水桝(しゅうすいます)の整備
|
|
次に、大雨の際などに水のオーバーフローを防ぐための「集水桝」を作成します。 皆さんも、道路の側溝の合流地点などが、広く・深くなっているところを見られたことがあると思います。あれが集水桝です。家の敷地についても、集水桝を作成することで、大雨時も穏やかに水を排水・浸透させることができます。 集水桝にする場所については、その土地の状況や環境、全体の水が集まる想定量を考慮した上で掘り返す形や深さを決めていきます。今回は、この桝の底部にも所々に点穴(縦穴)を掘り、水と空気が循環するようデザインします。 |
|
|
底面に炭を敷き、その上からグリ石を敷き詰めます。 |
|
|
さらに上から、枝葉を敷き詰めていきます。
|
|
|
最後に土を被せて完了です。 以上のように、土中環境整備は手間がかかる作業ですが、丁寧に施工することで氣水の流れは劇的に変わり、長く健やかな環境を保つことができます。 土中が健やかな土地では氣水の滞留が起こりにくいため、湿気やカビ、建物の傷みも発生しずらくなります。 |
次工程について
今回はSTEP3の排水に関わる土中環境整備の様子をご紹介しました。
次工程は、建物に沿った水脈の整備に関わる土中環境整備を実施します。
今回ご紹介した土中環境整備は、重要性の認知が十分ではなく、施工できる業者は限定的です。
湿気対策をしても改善しない、家の傷みが激しい、空気の淀みや嫌な臭いにお悩みの方は、ぜひ山匠にご相談ください。
<このような施工を検討中なら無料相談へ>