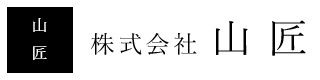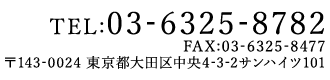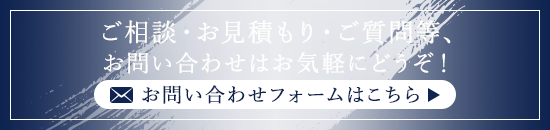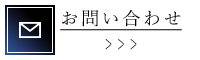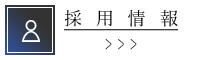「家全体から変な臭いがする」「押し入れがカビ臭い…」「床がきしむ音が気になる」
最近、このようなご相談を受ける機会が増えてます。
これらは床下の湿気が原因の可能性が高いです。
1月に「徹底解説!床下の湿気対策」というブログを掲載しましたが、多くのアクセスをいただくなど、家の湿気問題は多くの方々の関心事です。
住宅の床下は、外気との温度差や地面からの湿気により、湿度が高くなりやすい場所です。湿気を放置すると、カビや腐朽菌の繁殖、シロアリ被害、さらには家の寿命を縮める原因になることもあります。
本記事では、床下の湿気が引き起こすリスクとその対策として注目される床下リフォームについてより深堀して解説したいと思います。
なぜ床下の湿気対策が必要なのか?
- カビや結露、木材の腐朽リスク
床下の湿度が60%以上になると、カビや結露が発生しやすくなります。これにより、木材が腐りやすくなり、家の構造体に深刻なダメージを与える恐れがあります。 - シロアリ被害の原因にも
湿った環境はシロアリにとって理想的。特にヤマトシロアリは湿気の多い床下を好み、気づかないうちに家の土台を食い荒らしてしまうこともあります。 - 健康被害のリスク
カビの胞子やダニの繁殖が進むと、アレルギーや喘息など健康被害にもつながる可能性があります。特に小さなお子様や高齢者がいるご家庭は要注意です。
よくある湿気対策方法
特にお問合せが多いのは、床下調湿剤と換気扇設置です。これらはどのような施工なのでしょうか?
<床下調湿剤>
炭やゼオライトなどの素材を使い、湿度を吸収・放出する製品です。床下調湿剤は広く知られた対策で、個人での実施も可能な対策ですが、メリット・デメリットがあります。
床下調湿剤のメリット
・手軽に導入可能
・一定の調湿・脱臭効果あり
床下調湿剤のデメリット
・効果範囲に限界がある
・換気が悪いと効きにくい
・定期的な点検・交換が必要(湿気を吸い込みすぎると飽和状態になる)
床下調湿剤は、手軽に導入できる反面、単独では効果が限定的で、床下環境の改善を同時に進める必要があります(石灰を使った湿気対策記事もよく見ますが、石灰は吸湿後に調湿能力を失うため、短期間の効果しかありません)。また、定期的なメンテを怠ると、逆にカビや菌の温床となり、健康被害につながる可能性も指摘されています。
<床下換気扇>
電動ファンで床下の空気を強制的に循環させることで、湿気を外に逃がす手法です。
こちらも広く知られた手法で、簡単ではないですが、DIYで施工された方のブログを見かけることもあります。
しかし、床下換気扇の設計には注意すべき点もあります。
床下換気扇のメリット
・床下に自然換気口が少ない住宅では効果的
床下換気扇のデメリット
・通気設計が難しく、かえって湿気が溜まる場所ができることがある
・外気を取り込むことで結露リスクが増すことがある
(あたたかな床下との温度差が結露が発生)
・騒音が発生することがある(換気扇の老朽化や、設置場所が原因)
以上のように、リスクもあることから、施工は専門家に委ねるとともに、後述する床下リフォームの中で、必要性を判断すべき対策だと考えます。
効果的な湿気対策としての「床下リフォーム」
根本的に湿気を改善するには、専門家による、家の環境に合わせた床下リフォームがやはり有効です。家の土台に関わる事項であり、家の快適性に大きな影響も与えることから、専門家による家や土地に合わせた対策が重要と考えます。
<基礎部分にも種類がある>
一般的に住宅に使われる床下の基礎については、以下の2種が一般的です。基礎の種類に応じた施工の選択も必要になります。
・布基礎
床下は土のイメージがある方は多いと思います。これを布基礎といい、かつては主流でしたが、地面からの湿気があがりやすいため、もしこのタイプの基礎であれば、より根本的な対策が必要です。
・ベタ基礎
最近の住宅で一般的なのは、床下を防湿シートとコンクリートで覆ったベタ基礎と呼ばれるタイプです。
地面からの湿気を抑制する効果がありますが、湿気が多いと、ベタ基礎であっても湿気問題が発生してしまいます。
基礎部分のタイプに合わせた床下リフォーム
では、どのようなリフォームが有効なのでしょうか?
以下に施工例を例示します。
- 布基礎へのリフォーム
床下が土になっている布基礎については、地面からの湿気対策が必要です。そのため、土壌に「防湿シートを敷設」 する対策が考えられます。また、合わせて最適な「調湿剤の設置」を検討します。その際には、自然素材であり、効果も長い「川砂や炭の設置」 も有効です。合わせて、床下の状態に合わせて、「換気口の追加や調整」(必要に応じて換気扇も検討)、「木部防腐処理」等を検討します。 - ベタ基礎へのリフォーム
コンクリートで覆われたベタ基礎については、防湿シートの敷設はできないことが多いです。そのため、コンクリート上への「調湿剤の設置」(川砂・炭も検討)、 「換気口の追加や調整」(換気扇も検討)・ 「木部防腐処理」を中心に検討することになります。 - 基礎下のリフォーム:土中環境整備
施工可能な環境は限られますが、「土中環境整備」は有効な手段です。家の基礎下の土中内の空気・水の流れを改善する施工をすることで、土地そのものの環境改善を図れることが特徴です。湿気の多い土地に対してはこちらも検討します。
これらを組み合わせることで、長期間にわたって効果が持続する湿気対策が実現できます。大切なのは、家の建つ土地の性質を見抜き、最適な施工を組み合わせて実施する専門性です。
山匠は、床下リフォームで多くの施工実績を持つことから、床下の湿気でお悩みの方はぜひお問合せください。