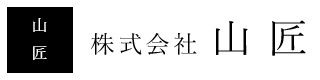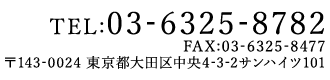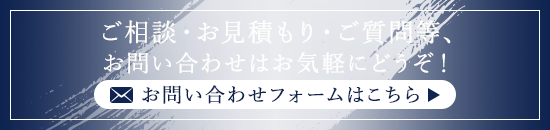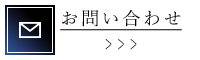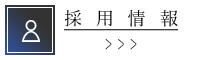戸建て住宅で湿気が問題になる原因は、建物の構造や周囲の環境、生活習慣が大きく関係しています。以下に、住宅で湿気が問題になる代表的な原因について詳しく説明します。
気密性の高い現代住宅では、自然な空気の換気が少ないため、室内が多湿になりやすいです。特に冬の季節や雨の日には、室温と外気との温度差が大きいため結露も起こりやすくなります。室内の湿度が高い状態では、結露が起きたり、カビの発生したりします。
断熱材不足と断熱材欠陥や断熱材が適切に施工されていないと、湿気に悩まされます。断熱性能が劣る場合、室内と外部の温度差が壁や窓際などで大きくなり、結露が発生しやすくなります。冷たい外気が窓などを伝わると、室内の湿気が水滴として現れる現象が結露です。結露が発生するとカビが増殖して住環境を大きく低下させます。断熱不良が疑われる場合は、断熱材の性能と量などが十分であるかを調べてみることをお薦めします。
現代の住宅はエネルギー効率を高めるため、気密性が高くなる傾向があります。特に、湿度の高い部屋(浴室やキッチンなど)では湿気がこもりやすく、結露やカビの原因となります。
日常生活の中で発生する湿気も、住宅内の湿度を高めることになります。具体的には、以下のような生活習慣が影響します。
• 入浴:浴室の換気が十分でなく、湿気が居住スペースに移動する。
• 料理:料理をすることで発生する蒸気が室内にこもる。
• 洗濯・乾燥:室内で洗濯物を乾燥させることで、室内湿度を上げる。
• 観葉植物:観葉植物を屋内に置くと、植木鉢などの水が蒸発し湿度を上げる。
断熱材には多くの種類があり、不適切な断熱材の使用や施工不良があると、壁の内部に湿気が集中しやすくなります。 断熱材が湿気を吸収してしまう場合や、断熱材が適切に施工されているないと壁内で結露が発生し、カビや劣化が進む原因になります。
湿気がこもりやすい建物設計も、湿気問題を引き起こします例えば、北側に窓が無い・北側風通しの悪い間取りなどです。
室内の温度が正しく保たれていないと、温かい空気が冷たい壁や窓に触れることで結露が発生しやすくなります。特に冬場のように外気温が低い時期には、室内の温度差が結露しますを気をつけて、湿気が増加する原因となります。
土中環境が関与する湿気トラブルは、床から蒸発する水分や毛細管現象による水分の吸い上げが主な原因です。対策が適切でない場合に問題が顕著になります。粘土質土壌は水分保持力が高く、排水性が悪いため湿気がしばらく滞留します。
まとめ
住居内の湿気の原因はさまざまです。建物構造や、住居が建っている土中の環境のように、対処の難しいものも多いです。長く住む住居を少しでも居心地のよい空間にするためにも、一度専門家にご相談してみてはいかがでしょうか。㈱山匠も、住居の湿気対策でたくさんの知見がありますので、お気軽にお問合せください。